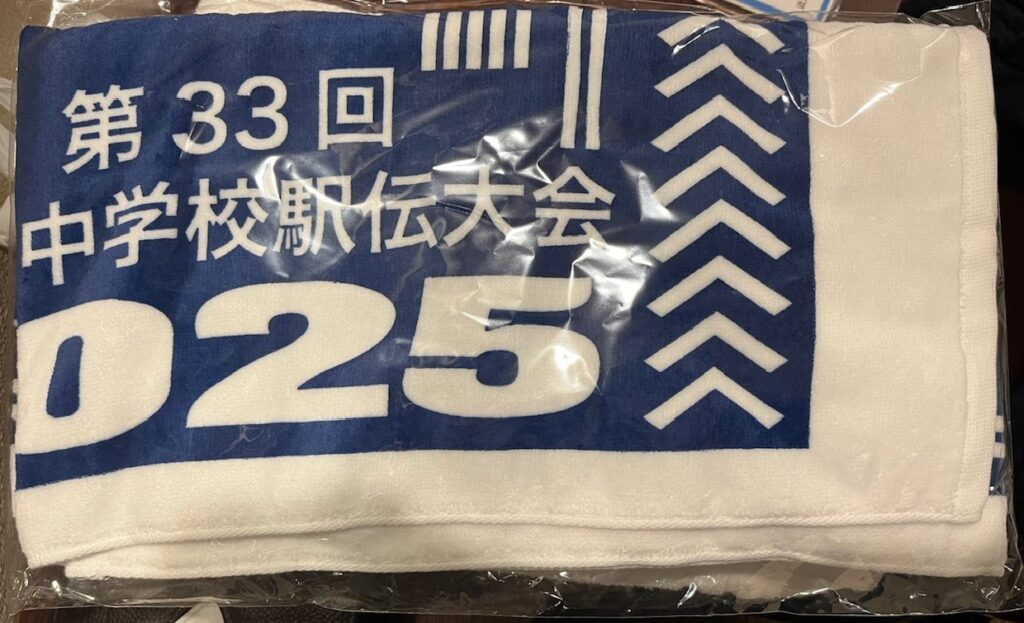大淀中陸上部外部指導者の中園です。主に長距離を担当していますので、顧問の河野先生より依頼を受けて全中駅伝の振り返りをさせて頂きます。
まず結果としては、57分38秒で1位と37秒差の県勢過去最高順位である準優勝でした。プランとしては、1区2区で先頭争い・4区を中心に中盤粘ってアンカー勝負というものでしたが、2区が終わって先頭とタイム差なしの2位と、前半から非常に理想通りの展開になり優勝に届くか?と思わせてくれました。が、ライバルが予想以上の強さでジリジリと離されてしまいました。
ただ、選手達は本当に我慢強く走ってくれて今持てる力をほぼ100%発揮できましたので、優勝には届きませんでしたが悔いはありません。…というただの報告で終わってしまうと、今回の貴重な経験が宮崎県のためにならないですし、この2年大舞台で持てる力を発揮できた理由と思えるエピソードもありますので、せっかくの機会ですので少し長くなりますがここまでの経緯も話させて頂きます。
今年のチームは昨年の全国8位という結果を受けて、子供達が「全国優勝」という大きな目標を立てて新チームがスタートした訳ですが、チーム作りという観点においては私の中では楽をさせてもらった1年だったと思っています。と言うのも、昨年卒業した先輩達が1から作り上げてくれた「自分が強くなるためにやるべき事をしっかりやる、努力するのは当たり前」というチームの雰囲気を後輩達が引き継ぎ、長距離ブロックの男女全員が私が練習に行けない日(本職が消防士なので週に1~3日程度しか行けません)に指導者がいないからと手を抜く事なんて彼らにはありえませんし、また部活の休みの日に自主的に練習をしたりと「当たり前の努力」を続けてくれました。
強くなるために足に不安があると「故障したくないのでメニューをこれに変えたいです」と言ってきますし、「今自分はここが弱いのでメニューを考えてくれませんか」という事も言ってきます。サボる理由ではなく、本当に強くなりたい気持ちが溢れています。また、長距離の天敵・貧血にならないために栄養を考えて食事をしたり(もちろん保護者のみなさんも熱心にサポートして頂いてます)、キツい練習をしてそこからしっかり回復して強くなるために早寝早起きをしたりと、高いモチベーションに波を作らず本当にやるべき事をしっかりと取り組んでくれました。
準優勝したメンバーは小学生時代から陸上をしている子達ではありますが、小学生で市町村対抗駅伝の宮崎市代表として走った子は1人もいません。そんな子達でも走る事を楽しみながらコツコツと努力すれば、大きな成果に繋がるという良い見本になったかなと思いますし、大舞台だからと自分を見失う事なくいつも通りの走りができたのはこの辺の理由があるのではと考えています。
また、今年の宮崎の長距離界では、他校においても田野中の河野くんや太田くん、高岡中の平田くんなど自分が強くなるためのひたむきな努力を続けて中学長距離男子の超一流の証・3000m8分台に到達した子が出ていますので、中学生は考え方や取り組み次第でどうにでも変われる年代だと改めて感じた1年でした。
今回の結果が、これまで「自分にはどうせ無理だ、才能がない」という気持ちになっていた子達の考えに一石を投じる事になれば幸いです。長々と書いてしまいましたが、最後に、特に今年1年は他校の先生方や地域の方々など多方面から私や子供達にお声掛けを頂き、本当に力を頂きましたし大変感謝しています。昨年含めてこの2年間で貴重な経験をさせて頂きましたので、この経験を宮崎県に還元していけるよう引き続き頑張りたいと思います!
それと、まだお話した事ない先生方や、子供達が沢山いらっしゃいますので、いつでも気軽に話しかけて下さい!そして勉強させて下さい!【大淀中外部指導者:中園】